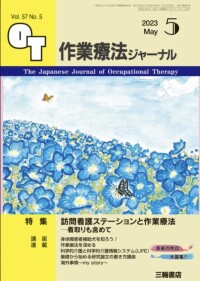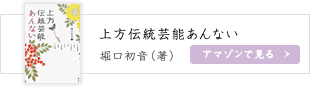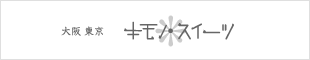「日高河清姫図」
7月15日(土)に「古道成寺」を舞いますので、村上華岳の名画「日高河清姫図」をぜひ観たいと思い、東京国立近代美術館「重要文化財の秘密」展に行ってきました。
国立近代美術館70周年記念だそうで、展示されている作品がすべて重要文化財という、ずいぶん贅沢な展覧会でした。
さすがの見応え。
上村松園や岸田劉生の作品はやっぱり圧倒的な存在感でしたし、高村光雲「老猿」はあまりの迫力に鳥肌がたちました。小出楢重「Nの家族」は初めて実物を拝見しましたが、印刷物で受けていた印象とはまったく違う、とても洒落た雰囲気で驚きました。
目当ての「日高河清姫図」は、蛇体になる前の清姫が描かれていて、儚げで悲しく、じっと観ていたら涙が出てきました。白くて小さい足が、ただただ哀れで。つらい恋を経験されたことのある方がこの絵をご覧になれば、カタルシスを感じるのではないかと思いました。「古道成寺」を舞わせていただくのは3回めですが、清姫のイメージがふっと固まった気がしました。
「日高河清姫図」は、清姫の可憐さを強調するような表装も素晴らしく、会期最終日にぎりぎりすべり込みで伺ったのですが、本当に観ることが出来て良かったです。
村上華岳は「描くことは祈りに通じる」が持論だったそうです。僭越ながら私自身も「舞は祈り」だと感じていますので、力をいただいたような、正しく導かれたような気持ちになりました。
PARCO劇場「夜叉ヶ池」
お稽古にお越しのお弟子さんが出演されるので、お招きいただきPARCO劇場「夜叉ヶ池」に行ってきました。
「夜叉ヶ池」といえば、坂東玉三郎さんの舞台や映画の印象が強いので、どんな演出で、どんなふうに演じられるのか、とても興味がありました。
大好きな森山開次さんが振付をなさっていたのですが、泉鏡花の世界にぴったり。美術や衣装も素晴らしく、新しい感覚の「夜叉ヶ池」を堪能しました。
開演前には、お弟子さんが所属されてる事務所の社長さんがわざわざ客席までご挨拶にお越しくださり、恐縮してしまいました。
とても熱心にお稽古に通っておられ、稽古場でも人気者でいらっしゃいます、とお伝えしました。
現在、稽古場には3名の女優さんが通ってきておられます。
皆さん本当に熱心で、頭が下がる思いです。
着物での姿勢や所作をきっちり身につけておられる役者さんが、もっと増えると嬉しいなと思っています。
「夜叉ヶ池」は5月23日まで。
ご縁のある方にぜひご覧いただきたいお舞台です。
鉄砲洲稲荷神社ご奉納
ご縁があり、八丁堀の鉄砲洲稲荷神社さまの例大祭にて、舞を奉納させていただきました。
高層ビルのなか、エアスポットのような江戸情緒あふれる空間。
ご由緒ある神楽殿で、爽やかな5月の風が吹くなか、なんだか私たちも清めていただいた気がしました。
まず若静弥『浦島』、そして若静花『潮来出島』、それこら若静雪『松づくし』、最後に若静紀『ぐち』。
たくさんの方が熱心にご覧くださり、嬉しかったです。
お優しくて楽しい宮司さまはじめ、神社の皆さまがとても親切にお世話くださいました。
また来年も、どうぞよろしくお願いいたします。
よし梅 地唄舞体験
毎年恒例、人形町の老舗料亭「よし梅」さんで開催される、GW特別企画。
今年は地唄舞の体験講座をいたしました。
まず地唄舞や山村流についてご紹介。
それから『弓張月』をご覧いただき、そして本日の課題曲である『落し文』を実演。
それから全員で、4分ほどの『落し文』をすべてご体験いただきました。
はじめて日本舞踊に触れる方、ご経験がおありの方、いろいろでしたが、皆さま素晴らしく「スジが良い」方ばかり。
しっかり時間内に終えることができ、最後は拍手拍手、でした。
ご体験のあとは、お楽しみの「よし梅」さんの美味しいランチ。こちらにさらにお椀とデザートがついています。
着付小物を作っておられる「たかはしきもの工房」の高橋和江さま、着物雑誌「月刊アレコレ」編集長の細野美也子さまもお越しでしたので、全員で着物のこと、また船場文化のことなど、和気藹々と楽しくお話しました。
「思った以上に楽しかった」「からだが喜んでいる感じ」と嬉しいご感想も。
あいにくの雨模様でしたが、ほっこりとしたひととき、幸せな時間でした。
お越しくださった皆さま、いつもお世話くださる「よし梅」さん、本当にありがとうございました。
『作業療法ジャーナル 5月号』
ご縁をいただき『作業療法ジャーナル 5月号』巻頭コラムを書かせていただきました!
養老孟司先生や群ようこ先生はじめ、これまで錚々たる先生方がお書きになってるので、とても光栄です。
タイトルは「〈こころ〉を表現するために」。
ご興味をお持ちくださいましたら、ぜひお読みください。